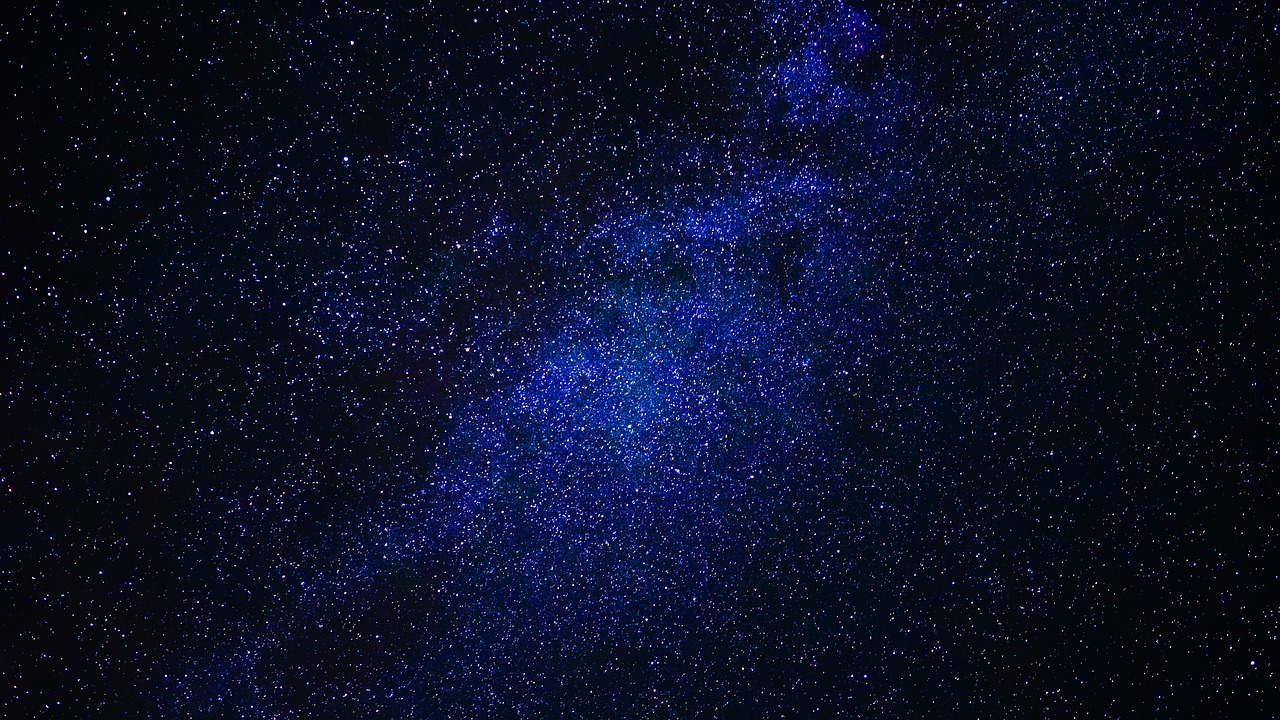私たちが普段使っているものは「化学」とは縁を切っても切れません。金属の膨張、収縮、電気抵抗を利用した測定法があります。今回は体温計についてとりあげてみたいと思います。
※ 体温計には水銀体温計、電子体温計、耳式体温計の3種類がありますが、ここで挙げているのは、電子体温計の前の世代で使われていた水銀の体温計です。
Contents
体温を普通の温度計で測ってもいいの?
もちろん、普通の温度計でも測れます。測れるのですが、問題があります。なぜでしょうか? そうです。温度計を脇から出したら、温度が下がってしまうのです。普通の温度計はひとりで上がったり下がったりするからです。
体温を測る前にどうして水銀体温計をふるの?。
普通の温度計はひとりで上がったり下がったりしますが、水銀体温計はひとりで下がってくれません。水銀体温計で体温を測ってそのまましまうと、次回使う時も水銀柱は前回の温度で止まっています。だから、「ふって」水銀柱を下に下げてリセットする必要があるのです。
ふらないと、温度が下がらないのはなぜ?
Q: 下図の体温計にはどんな工夫がされているでしょうか?
① 20190623-1024x653.jpg)
左の普通の温度計は球部から上に伸びる細い管の太さは同じです。
水銀体温計は球部の上が細く(留点部)くびれています。水銀が膨張して上に上がるときは普通の体温計と同じように上がります。しかし、収縮するときは右図のように上の部分と下の球部は別々に収縮するので水銀柱は留点部で切れます。だから、右図のように上に上がった水銀柱は上がった所で止まります。
温度が上がって、水銀が膨張すれば水銀柱は上に上がり、冷えれば収縮して下がります。
つまり、「ふる」ということは水銀を収縮させて水銀柱を下に下げるということです。ふって体温計をリセットさせているのです。この水銀の性質を利用しているから、水銀体温計は脇から出しても温度が下がらないのです。
水銀はどんな性質をもっているの?
温度が上がるときは膨張していて下がるときは収縮しています。そもそも水銀の膨張や収縮って何だろう・・・。
「あれ?」「なぜ?」って疑問だらけになります。この謎を解き明かすに「化学」が登場します。
熱伝導と膨張を利用
熱伝導とは
高い温度側から低い温度側へ熱が伝わることです。
熱いお茶を入れた湯呑が熱くなるのも、お茶の熱が湯呑に伝わったからです。
膨張とは
体積が増えることです。温度が上昇すると、気体・液体・固体に関係なく物質は膨張します。
電線は暑い夏にはだらんと垂れ下がっていますが、寒い冬にはピンと張っています。夏は熱で導線が膨張して伸び、冬は収縮(ピンと張る)するからです。
まとめ
水銀体温計は体の熱が水銀に伝導、温度が上がった水銀が膨張して水銀柱が上に上がります。収縮しなければ水銀柱が下がらない性質を利用しています。
体温計以外にも、膨張、収縮、体積、電気抵抗、圧力を利用した測定法があります。はるかかなたの星の温度もこのような性質を利用して測ることができるのです。
私たちの身の回りのものは何のどんな性質を利用しているのだろう、その疑問を解き明かしてくれるのが化学と物理です。
※ 化学のドレミファ3 熱の正体がわかるまで 14 マリコさん、カゼをひいて熱を出す